長崎学のページ

プロローグ・プロローグ
長崎楽会という長崎の歴史や話題を楽しむ会があります。長崎楽会は、月一度の例会を持ち、それぞれが興味を持っている分野でレポートを行い、情報の交流を深めています。
長崎楽会の新米会員として私は2000年12月27日、上記のテーマでレポートをしました。
このページは長崎楽会での発表を加筆修正したものです。
レポートに当り、インターネットでの本の検索を大いに利用し、久しぶりに図書館や本屋さんで書籍集めをしました。
国会図書館、都立図書館ともネットでの検索システムが一昔前に比べるとずいぶん便利になりました。
けれども、理想は本の内容をwebで閲覧できる事です。
著作権の問題など解決しなければならない問題がありますが、近い将来全ての資料をネット上で安価に誰もが入手できるようになって欲しいと願っています。
前置きはさておき、「醤油」の話です。
プロローグ
醤油なしでは考えられない日本の家庭料理ですが、今のような醤油が一般的に使われ出したのはそんなに昔の事ではありません。
一般に普及しだしたのは江戸時代も中期です。それも、比較的余裕のある武家や町人社会でのこと、人口の8割を占める農村では江戸時代は依然として自家製の味噌が調味料の中心でした。
ですから醤油なしでは成立しない、にぎり、蒲焼、佃煮などが万人の口に入るようになったのは案外最近の事なのです。
ところが、長崎の出島ではかなり高価で一般に普及していない江戸時代初期から醤油は海外へ輸出されていました。
醤油は出島からの主用輸出物ではありませんが、それでもセラミックロード(海のシルクロード)を通って幕末のころにはかなり大量の醤油がアジア、ヨーロッパへ渡り、誰もが知っている高価な調味料としての地位を築いていました。
幕末、日本の開国による貿易自由化に伴い、粗悪品や贋物の醤油が輸出されたこと、また中国醤油との価格競争に敗れたことが原因となって、長崎からのヨーロッパへの輸出は明治以降次第に減少し、長崎出島ブランド・コンプラ醤油は忘れられていきました。
あまりに優れた調味料、醤油の存在故に日本料理が素材に傾き、料理法の発展を阻害したとの見方も存在しますが、ヨーロッパで日本醤油が駆逐されることがなかったら、ヨーロッパの料理ももっと変わっていたかも知れません。
レポートにあたり以下の文献を参考にさせていただきました。
- ・ 醤油から世界を見る
- 田中則雄 崙書房出版
- ・ しょうゆ 世界への旅
- 大塚滋 東洋経済新報社
- ・ しょうゆ 味の旅
- 河野友美 玉川選書
- ・ お醤油の来た道
- 嵐山光三郎/鈴木克夫 徳間書店
- ・ 東と西の醤油史
- 林玲子/天野雅敏 吉川弘文館
- ・ 江戸料理史・考
- 江原恵 河出書房新社
- ・ 長崎の西洋料理
- 越中哲也 第一法規
醤油について
醤油の仲間の発酵調味料
- 肉(後に大豆)+麹(雑穀・米・麦の)+塩+酒 (発酵)→醤[ひしお]
- 大豆+麹(米+麦)+塩 (発酵)→味噌
- 豆麹(+塩) (発酵)→くき
- 豆麹+塩 (発酵)→溜(たまり)、溜味噌
- 醤油麹(大豆と煎った小麦)+塩 (発酵)→醤油
醤油のルーツを遡ると1の肉を発酵させたもの、肉醤(にくびしお)にたどり着きます。これは塩辛のようなものです。タイやベトナムなど東南アジアではナンプラー、ニョクマムなど魚を使った醤(ひしお)、魚醤(ぎょしょう)が今も最もポピュラーな調味料です。
2はお馴染みの普通の味噌。
3は「倭名類聚鈔」に調味料として登場しています。「延喜式」では大豆と海草を用いて作る製法が記述されています。浜納豆、大徳寺納豆のようなものではなかったかと考えられています。
4は現在、愛知、岐阜などで多く作られている豆味噌の一種です。仕込むとき水分を多くしたものが溜味噌です。
5が普通の醤油です。
1、2は麹の力をかりて発酵させますが、3、4、5は豆そのものを麹に変えるというい違いがあり、よりうまみ成分が多いといえます。
現代の醤油製造工程
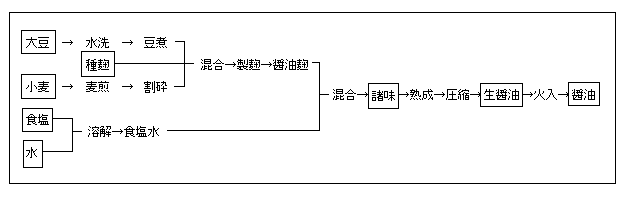
大豆は普通、脱脂大豆が使われます。丸大豆醤油とというのは脱脂大豆ではない普通の大豆のことです。
昔は自然発生の麹カビを利用していましたが、今は醤油醸造に適した麹カビを培養、保管した種麹を使います。蒸した大豆、煎って割った小麦、種麹を混ぜて30度、湿度100%の室に入れ、3日ほどかけて製麹(せいきく)し、醤油麹を作ります。
醤油麹と食塩水を混合したものが諸味で攪拌しながら熟成を待ちます。熟成期間は半年から1年近く、熟成した諸味を圧搾したものが生醤油(なましょうゆ)です。
生醤油は不安定なので、酵素の働きを止め雑菌を除去するために85度cくらいで火入れをします。生醤油も一部流通していますが、多くは火入れしたものが流通しています。
生産の現状
日本人の平均消費量は約8.8リットル/年で、現在作られている醤油の種類とその生産割合は下のようになっています。
| (1)濃口醤油 | 84% | 大豆・小麦が半々 |
|---|---|---|
| (2)淡口醤油 | 13% | 発酵、熟成を抑えるために塩分が1割多い(18%) |
| (3)溜醤油 | 2% | 小麦をほとんど使わない |
| (4)再仕込醤油 | 0.3% | 仕込に食塩水ではなく生醤油を使う |
| (5)白醤油 | 0.7% | 溜醤油と反対に大豆をほとんど使わない |
日本の醤油のルーツ
一般には鎌倉時代の禅僧、覚心が醤油作りを広めたと言われており、湯浅醤油のラベルには「醤油発祥の地八百年の伝統」と唱ってあります。
覚心は、13世紀の半ば、中国、浙江省にある径山寺で6年間の修行を積み帰国後、紀州・由良(和歌山県湯浅町)に西方寺を開きます。虚無僧の開祖でもある覚心は、径山寺で学んだ味噌作りを広めました。たまたま水分量の多かった味噌の上澄み液で煮物を作ったところ、それが大変美味しく、ここから醤油作りが始まったと言われています。
当初、この溜まりは自家生産でした。商品化されたのは300年後の1580年ごろ、湯浅の「玉井醤」が味噌醤油業を始めたのが最初といわれています。
その後、潮流の影響もあって、紀州から多くの人と技術が房総半島へ渡りました。 1616年に摂津の田中玄蕃が、1644年には湯浅の浜口儀兵衛が銚子に渡り、醤油醸造業を始めたと言われています。
関東の醤油醸造は、湯浅から伝わった技術が江戸川・利根川沿岸の水運に恵まれた地域を中心に発達していきました。
野田では戦国時代に飯田家が醤油を製造したと伝えられていますが、これは「溜り醤油」でした。
近代醤油の製法が確立したのは17世紀後半といわれています。当初、江戸では「下り醤油」が上物とされていましたが、江戸という大消費地を背景に、技術も生産量も大きな飛躍をとげ、1821(文政4)年の江戸では123万/125万石が関東生産の地回り醤油だったという記録が残っています。
このように、醤油醸造技術は関西の溜まり醤油から発展した技術が関東に渡り更に発展して行ったものとされていますが、中国では明時代に醤油が一般に普及しましたから、日明貿易の中で、製品と共に製造技術も伝わったのではないかと考えられます。
後掲「出島と醤油」の項でとりあげるケンペルの『廻国奇観』(1712年)に記載されている醤油製造法を読むと、中国醤油の製造法に近いようです。
出島と醤油
ヨーロッパ人の醤油観
ヨーロッパの人々は醤油をどのようにみていたのでしょうか。文献に現れる記述から、出島からの輸出背景を考察してみます。
34年間日本に滞在し、信長にも謁見しているルイス・フロイスは、醤油にふれていません。この時代は調味料として醤油は使われていなかったと考えられます。
醤油と記述されていますが、湯浅で玉井醤が味噌、醤油醸造業を始めたのは1580年ごろで、それは近代の醤油ではなく溜まりのようなものであったと言われていますので、ここで登場するシャウユはいわゆる醤油とは違っていると考えられます。
当時、刺身は酢の類で食べていました。「酢に相当する」という記述は、シャウユが酢の代りに刺身の調味料として使われはじめている事を想像させます。
オランダ商館付き医師ケンペルは2年間の日本滞在中、日本の地理、気候、風俗、習慣、その他、社会全般について資料収集、調査をしました。それを元に帰国後、『廻国奇観』を著します。この著書はヨーロッパで大変な影響を与えた本です。
この中では、大豆は空豆と記述されています。この時代、ヨーロッパではまだ大豆が知られていません。大豆が知られるようになったのは19世紀になってからです。
中国産の醤油もあるが、日本産のものがはるかに優れている。肉料理にとって、日本産の方は中国産にくらべ、深く豊かな滋味を付与してくれるからである」
セラミックロードを渡ってヨーロッパに運ばれた醤油は、オランダからフランス、ドイツに輸出されていました。ルイ14世が醤油を愛用していたという話は有名です。
文中、ルルヴェという料理がどのようなものかレシピも残っていないので分かりませんが、ヨーロッパでは主に醤油はソースに混ぜて用いられたようです。
その代り、非常に上質の醤油を作る。これは支那の醤油に比して遥かに上質である。多量の醤油樽が、バタビア、インド、及び欧羅巴に運ばれる。互いに劣らず上質の醤油を作る国々がある。和蘭人は醤油に暑気の影響を受けしめず、又その発酵を防ぐ確かな方法を発見した。和蘭人はこれを鉄の釜で煮沸して壜詰めとし、その栓に瀝青1)を塗る。かくのごとくすれば醤油はよく、その力を保ち、あらゆるソースに混ぜることが出来る。
醤油は欧羅巴の各国にも輸入されているが、醤油豆(大豆)と裸麦或いは小麦及び塩で作られるものである。」
スェーデンの植物学者、医者であったツンベリーは出島商館付医師として来日しました。商館長の江戸参府に従い、数々の資料を収集し、帰国後、『日本紀行』を著しました。この中で醤油を変質させない方法をオランダ人が考えたことを記しています。多量の醤油樽が、バタビア、インド、及び欧羅巴に運ばれる。と書いてありますから、この時点ではまだ樽で運ばれていて、ヨーロッパに渡った後、瓶詰めが行われた醤油があると考えられます。
又腐敗せる魚にもあらず。醤油は実に小麦・塩・及味噌豆といえる白豆の一種の混合に外ならず。此等は大槽に入れて地下に貯えられ、一定時間の間発酵せしめたる後、之を煮沸し以って永く保存し得しむ。」
オランダがフランスに併合され、ジャカルタがイギリスに占領されたため、オランダ国が存在しない期間があり、蘭船の出島への来航は1807~1817年まで1隻もありませんでした。その時の商館長(カピタン)がヘンドリック・ヅーフです。
この頃には日本でも火入れをして醤油を保存していたことが記されています。
気の毒なのは牛肉についての記述です。表向きは仏教の影響で江戸時代、鳥類を除いて獣肉を食さないことになっていますが、長崎では、郊外で豚の飼育が行われ、屠殺場もありましたから、豚肉を手に入れるのは簡単だったようです。
ただ、牛は農業の生産手段としての役目が重視されたこともあったのでしょう、肉牛はいませんでした。出島の絵に登場する牛の絵は、バタビアから船で運ばれた牛です。船旅で痩せてしまった牛は、一定期間出島で飼育し、太らせてから食用にされたそうです。
シーボルトは簡単にふれているだけですが、人の知る醤油という記述は、注目 されます。この時期、中国産であれ、日本産であれ、醤油はヨーロッパでは珍しい調味料ではなくなっていたということを意味しています。
通商条約締結のために来日し、長崎の町も歩いたプロシア大使のオレインブルグの記述は、いくつか注目すべき点があります。
- 大部分人工的に合成した化学製品と言う記述で、贋物が出回っていたことがわかります。
- しかも富裕な人々の食卓にだけ見られるものである。とは、更に贋物が高価であったことを示しています。
- ヨーロッパにもってきて馴化させたいものに大豆がある。と安価でおいしい醤油をヨーロッパで生産したいという意欲を表現しています。
ヨーロッパでの製造の試み
野田の東京醤油会社が輸出努力をしている時期。
実態に近い製法を記述しているがこの段階でも麹が知られていない。
のこの論文は、1712年頃出版された全33巻の百科辞典、『和漢三才図会』の醤油の製法、大豆の栽培を翻訳したものです。
けれども湿度の低いヨーロッパでは麹菌が知られていないため成功しませんでした。
野田の東京醤油会社が輸出努力をしている時期で醤油製造に関する情報量は増え、実態に近い製法が記述されていますが、この段階でも肝心の麹が知られていないため、成功していません。
ヨーロッパで麹が知られるようになったのは、パスツールまで待たなければなりませんでした。
結論
上記の文献から見える事は、幕末の時期にはヨーロッパでは「安くておいしい醤油」を渇望している状況がありました。製造の試みもありましたが、成功せず、日本の醤油輸出も貿易自由化の混乱が影響して明治以降減少して行きました。
醤油の普及で日本料理は大きな影響を受けていますが、ヨーロッパでは料理に影響を与えるまでに到らなかったといえそうです。
輸出ルート
醤油輸出の輸出先と量は全ては分かっていませんが、残っている資料からみると、日本では一般に醤油の普及していない江戸初期から輸出され始め、幕末にはかなり大量の醤油が出島から積み出されたことが分かります。そもそも、オランダのアジア進出は、香辛料貿易による利潤を求めたのが大きな目的であったことを考えると、醤油が早くから貿易品目に加えられ、オランダからヨーロッパ各地に輸出されていったことは当然の成り行きだったかもしれません。
しかし、醤油輸出のもう一方の重要な要因は、東南アジアの日本人や華僑向けの需要をみたすためでもありました。
出島からの輸出には下記の3つのルートがありました。
(2)オランダ商館、船員の脇荷輸出
(3)中国船による輸出
輸出先:(1)タイワン (2)トンキン (3)シャム (4)バタビア (5)マラッカ・カンボジア (6)コロマンデル・ベンガル (7)セイロン (8)スラッタ(インド西海岸) (9)アンボイナ・バンダ・テルテナ(モルッカ諸島)・マカッサル(セレベス島)
などインド及び東南アジアの各地域で、バタビアからは更にヨーロッパまで運ばれました。
出島からの最初の輸出は、複数の書籍、長崎のチョーコー醤油の「金富良縁起」では1668(寛政8)年と記していますが、最近の研究では、オランダ東インド会社長崎商館仕訳帳の記録、1647(正保7)年とされています。
出島ができて間もない時期に醤油は輸出されていたことになります。
残っている記録を記述すると
・ 1647(正保7)年 10樽 →タイワン商館→ベトナム(長崎商館仕訳帳の記録)
・ 1668(寛政8)年 12樽輸出の記録(ハーグ文所館)
・ 1693(元禄6)年 バタビアなど93樽
・ 1673(元文2)年 初めての会社輸出、75樽をバタビアへ、うち35樽をオランダへ
・ 1761(宝暦11)年~1790(寛政2)年
この間30樽~90樽
・1792年 10樽
・1793年 輸出止
1799年にオランダ東インド会社倒産し、オランダ領東インドは東インド政庁の統治下に入りますが、19世紀にも相当領量の醤油が輸出されています。
会社あつかいの輸出量にくらべ脇荷輸出の方が多く、
・ 1711(正徳元)年、会社輸出61樽に対し、脇荷は「味噌・醤油」合計で867樽
・ 1712(正徳2)年、会社輸出69樽に対し、「味噌・醤油」合計で999樽
という記録が残っています。そのうち醤油は半分以上を占めます。
・1712(正徳2)年、191樽
・1713(正徳3)年、388樽
(以上、唐蛮貨物帳印影本の記録)
・ 1804(文化元)年~1829(文政12)年、63樽~322樽
醤油価格
- 江戸時代初期は酒価格と同じ程度。贅沢品でした。
- 江戸中期以降、江戸、京都、大阪など都市を中心に調味料として普及しましたが、農村部では自家製の味噌および味噌垂れが調味料の中心で醤油は農村では依然贅沢品でした。
- 江戸後期に入ると各地で醤油醸造が盛んになり、農村にも醤油が普及してきます。しかしその一方で農村では自家醸造もされるようになります。
- 明治に入り、農村では醤油を自家醸造するものが輩出します 明治後期、大規模生産の歴史のある関東では自家醸造は少ないのですが、長崎では50%近くが自家醸造醤油であったと記録されています。政府は、自家用醸造に対して一時醤油税を設けたこともありました。
一方輸出された醤油の価格は輸送コストを考えたとしても相当のものでした。 - 幕末、オランダハーグでの価格は
『歐西紀行』を記した文久使節団の高嶋久也は、1升、1両(数万円)以上の値段で売られていたと書いています。
輸出逸話
その中、「東航紀聞」(紀伊藩)に醤油についての記述がみえます。
「メヒコ墨是可新話」(島原藩)
幕末には相当量の醤油が輸出されていましたから、アジア、ヨーロッパで入手可能な状況があったようです。
コンプラ瓶について
コンプラの語源 conprador はポルトガル語で"仲買人"という意味です。
オランダ人に日用品を売る特権を与えられた商人をコンプラ商人とよび、その組合をコンプラ仲間といいました。コンプラ瓶はコンプラ仲間が作っている「金富良商社」ブランドの瓶です。
波佐見焼きのコンプラ瓶に詰められた醤油が出島から輸出されるようになったのははっきりした年代は分かりませんが、幕末の頃と類推できます。
『波佐見陶史』(昭和44年)に古老の話の記述として次のように記されているそうです。
この蘭瓶は醤油三合入りの徳利であった。
40万本ものコンプラ瓶が長崎から輸出されていたのが、貿易自由化される1859(安政6)年以前か以降かは定かではありませんが、長崎港から輸出された大量の醤油瓶は、今もヨーロッパの古道具屋で目にすることがあるそうです。






右、大豆と小麦の絵入り。長崎<森山醤油>が1900年のパリ万博に出品した瓶か?
コンプラ瓶の文字の謎
コンプラ瓶には肩にJAPANSCHZOYAとだけ書かれているものと裏にコンプラ社を表すCPDの押印のあるものがあります。
JAPANSCHZOYAとだけ書かれているものは、比較的初期のもの、押印は贋物と区別するためにつけられるようになったので貿易自由化以降のものと考えられます。
また、JAPANSCHZAKYと書かれた酒瓶もあります。
ところが、オランダ語なら、醤油はSOYAであるはずが、なぜZOYAとなったかは以前から謎とされていました。
現に、JAPANSCHSOYAと書かれている瓶もありますが、大半の瓶が"z"です。
日本ジョーユとにごったという説、"s"と"z"の単純なスペルミス説、日本酒造屋説といくつかの説がありますが、長崎楽会例会発表後、長崎楽会メーリングリストで語学の専門家である会員の郷農さんが説得力ある説明をご披露されました。
"ドイツ語では「日本の」と言う形容詞がJapanischで、醤油がSoyasauceなので、その音声から日本語ではヤパーニッシュゾーヤ(ゾース)となり、もう1回それを欧語に変換するときにiが欠落し、(S)が(Z)になったものと推察します。"
音声でのヤパーニッシュゾーヤがJAPANSCHZOYAで定着してしまったと考えは他の説よりありそうな気がします。
井伏鱒二の短文「長崎の醤油瓶」について
輸出が皆無になり、すっかり忘れられた存在になっていたコンプラ醤油瓶ですが、この短文によって、ロマンチックで少しミステリアスなムードを携えて再び注目を浴びるようになりました。
井伏鱒二は、
「穴ぐらに埋められていた」というミステリアスな記述は、実は真実ではなく、当時の関係者の話では県庁が保管していた瓶であり、箇数も三百ではなく、三千箇だったようです。
徳富蘆花がトルストイを訪問したとき、コンプラ瓶を一輪差しにしていた話も披露してあり、
なるほど、プーチャチンに随行したロシア文学者のゴンチャロフがトルストイに進呈したという考察は全くありえない話ではないかもしれません。
けれども、徳富蘆花がトルストイを訪問したのは1907(明治40)年、トルストイが80才近くのことです。
幕末から明治にかけてロシアの東洋艦隊がウラジオストックの凍結をさけて冬期、長崎に滞在していた時期がありました。長崎では当然ロシア人向けの商業活動がありました。
醤油もロシア人向けの商品がありました。ロシア語で「ヤポンスキー」と書かれた醤油瓶が出て来ています。
トルストイの醤油瓶の文字がロシア語なら、幕末ではなく明治期のロシア向けの醤油瓶だったはずですが、それを確かめる術はありませんが、私はロシア語瓶であった可能性の方が高いように思います。