- 「ひがし」(1958版)
- 昭和33年1月20日
- 編集兼発行:長崎県立長崎東高等学校 全日制生徒会
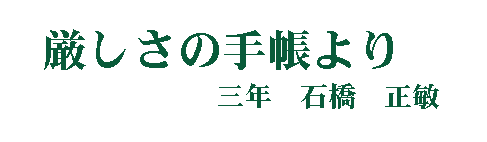
過去を反省して、回顧の記録を書くことは、やさしいようで、なかなかむづかしいものである。
忘れることが人間の特権だとすれば、それはまさしく現在のその人に対する暴力であり、拷問にも等しいものだ。品行方正成績優秀もって他の範ともなすべき徒ならともかくも、ふりかえってみて、よくも又、と思うほど、あそこにぶっつかりここにぶっつかり、のたうちまわった跡があるだけなのだから。
しかしながら、目茶苦茶にのたうちまわり、さて今は、と見れば満身創痍、そのあばれ方がひどければひどいほど、その傷が深ければ深いほど、傷ついた己を、かぎりなくいとしく思うのである。
中学時代の恩師が、「あなたくらい高校時代をやり放題やってきて、それでストレートで大学に入ったら、一年生の時からこつこつやってきた人に申しわけないと思いなさい。」とおっしゃられたが全く、その通りなのだ。
入学して一ト月程、何もなく過ぎた。クラブへも入っていなかった。
五月のある日、友人に新聞部室へつれてゆかれて、"ソウム"とかいうものに立候補せろといわれた。僕は、そんな大それた事はいやだと断った。上級生が出て来て、友人が、その人に僕を紹介したが、いけすかぬ奴だったのであいさつもせずに、にたにた笑って相手にしなかったら、その上級生はきどった歩き方をして行ってしまった。さっぱりとした。しかし、とうとう立候補して、いつの間にか無投票当選となっていた。
ソウムのキリツ係とかいうものになったが、仕事が何だか解らなかったので出なかった。夏休みに、友人達と喧嘩をした。すべて、僕のわがままが原因だった。
九月の初め、同じ係の杉山君と校門の先の三つ角に立たされた。交通整理であった。週番交代は杉山君がやっていたので、キリツ係になって初めての仕事だった。彼は中学時代に生徒会をしていたので、僕は彼に対し敬意と恐れをいだいていた。
つくづくと、えらい奴等の集りに入ったものだと思った。
十一月に半数が改選となり、二年生がみんなやめてしまい、一年生のみの総務が組織された。生徒会の末期的な形相であった。"カイチョウ"にさせられた。何故僕がなったか、今もって解らないがたぶん総務室の掃除を毎日していたからだろうと思っている。今は亡き大場君が会計部長だった。
女生徒が四人いたが、皆、たくましい人だったので、甘いロマンチックな夢など起ろうはずもなかった。
就任式の日、中庭での新任の挨拶の時には何をいったか解らず、それが終わるとすぐにラグビー部の二年生が僕の前に立った。
「おいちょっと来てみんや。」
「何か用ですか。」
「よかけん、だまってついて来い。」
内心、えらいことになったなと思った。いわれる通りついてゆくことにした。両側に、二年生がついて歩いた。何やるんかなあ、でもいいや、それくらいは覚悟の上だ。部屋の前にくると戸口のところにも二、三人いた。
「入れ」と腕を引かれて、よろよろととしながら入ると戸がバタンとしまった。かんぬきがかかって、二人が戸口に立ちはだかった。
上級生がぐるっと僕のまわりをとりまいた。いちばん強そうなのが椅子をうしろ向きにしてすわっていた。三年生だった。もうオジサンである。それにくらべて、僕はまだボウヤだ。
「よう、どうしておい達に、だまってグランドばソフト大会に使うたか。」
「さあ、僕はよく知りません。でも一応断ってあったのじゃないんですか。」
「嘘つけ。おい達も運動場ば使う権利はもっとっとぞ。」
ちえっ、又、権利権利いやがる、馬鹿の一つおぼえみたいじゃないかと思ったが、例の調子でわからぬように深呼吸をして、にたっと笑うと、彼等の顔色がすこしさめた。
「しかしですねえ、ラグビー大会のときも使うから、おたがいさまでいいじゃないですか。」そういうと右側にいた二年生が
「そいばってん、おい達は練習せんば川口先生からやられるっとぞ、わい達はよかろうばってん。」とつばきをとばしながら、目をしょぼしょぼさせて云った。云いおわるとよだれがだらっと出た。又にたりと笑うと、てれくさそうに、持っていた棒を折って、ふりまわしまがら地面に投げつけた。
「それじゃ、川口先生に僕がおわびに参りますから。」というとまだぶつぶつ云っていたが、「ラグビー大会の時は賞品ばよけいだせよ。」といって戸をあけた。
にたっと笑って、例の外交礼儀で、ていねいに挨拶をして外に出た。戸口には前の会長の人が心配して来ており、中に入ってきて部員と話を始めたが、部員も僕に対するほどはいばっていなかった。
今ほどはひどくなかったが、しばしば代議員会も流会をし、当然それが問題化した。流会といっても、今のような昼休みの代議員会ではなく、流れない時は、時間も規定の二時間をオーバーするのが常だったし、電燈をつけて114教室で討論がなされた。全く寒い室だったが、論戦でさほど気にならなかった。
流会対策として、生徒の生徒会に対する関心を高めることと、代議員の待遇改善が大きく上り、他に細目が定められた。臨時生徒大会を開くためであった。学期末考査の1週間前であった。
僕にとっては初めての生徒大会で、まったく興奮していた。しかし、それは僕のみではなかった。全生徒がそうであったし、一時間の時間が終っても生徒は教室へ帰ろうとはしなかった。僕は全く興奮して、生徒をかきわけては演壇に上り、わめいたりやじられたりした。
代議員の待遇改善に関しての放課後おそくや、土曜日の代議員会にはパンを出すことという案が出された時には、講堂がわれるほど騒いだ。パン屋の人が二年生にいたが、その人が、「パンにつられて、東高の代議員が出るなんて、東高はそんなにおちぶれたんですか。」と泣きそうな声で真赤になって叫ぶと、皆は爆笑して「そうだ、そうだ。」と叫んだ。
代議員は信用をおとし、なっちょらんといわれ、反対に、代議員よ反省せよといわれるはめになってしまった。
すぐに代議員会が開かれ、総辞職を決議し、声明を行ったが、生徒の反感はものすごかった。僕は、すぐに室長会議を招集して、各クラスの意見をまとめた。代議員会は総辞職を取り消し、大局的見地から行動せよとのことだった。
再び、会長職権で代議員会を招集した。総辞職は、会長不受理とし、代議員会は取下げをした。
そこで、生徒会に対して全生徒がなお一層関心を高めるよう、議長と会長が演説をぶつことになった。中庭に全生徒が集められた。
まず議長が登って、経過を説明し、協力を要請しようとした。生徒が騒がしかったので、声をはりあげていたが、遂に怒って「バカヤロー、自分達の生徒会のことじゃないか…」といった。皆、怒りだした。
天満屋先生が登って「少しは真剣に考えたまえ。自分達の生徒会を運営出来ないでどうするか。」といわれた。
僕が立って代議員を目茶苦茶にこきおろした。もう度胸もついてふるえなかった。人でなしだのわがまま者だの、ありったけの悪口をいったので、皆、ぽかんとして聞いていた。
「バカヤロー」問題で再び代議員会は召集され、議長不信任が出された。伊藤議長は辞任して、高野議長が就任した。しかし、そのまま冬休みで代議員会は開かれずにしまった。試験は目前だった。
僕は盲腸の手術で入院した。これほど荒れねばならない生徒会の現状も次第にわかるような気がした。でも、僕の全力をつくす他はどうしようもないと考えた。退院したのは、ジングルベルが鳴っている頃だった。
家の者には嘘をついて学校へ行った。もうすでに冬休みだったが寝たままで動かれなかったのであきあきしていたから、早々と、とびだした。そろそろと歩いていった。家の者には、生徒会をしているのは、ないしょだった。
元旦には祝賀式があった。
倫平先生(校長を梅田先生と呼んだことはなかった。梅干しとよぶにはおそれ多かったので、倫平先生と呼んだ。その方が親しみがもてたし、時には倫平サンとも云った。)が、元旦の挨拶と抱負を述べられ、次に生徒代表として云わねばならなかった。原稿はなかったので、何をしゃべろうかと考えたが、頭が一向にまとまらなかった。
倫平先生は「門松や冥土の旅の一里塚」と三度ほどいわれた。
そんな爺くさいこというから梅干しなんていわれるんだ、よし、「若さ」を誇ってやれ。先生の話が終ったので、ちょこちょこと出ていった。すらすらと、こんな意味の言葉が出た。
「新しい年昭和31年、その新しいものの中に私達は、過去の楽しかった事、嬉しかった事、苦しかった事の積もり積もった現れが現在の姿なのだというなんとも表現出来ない気持ちにおそわれると同時に、過去を反省し、未来をよりすばらしいものとするために、現在を力強くふみしめ歩まねばならない――。
私達は若い、まだ若いのであります。若人の意気に燃えつつ、あくまでも学生たることを忘れずに――。
私達はこの日『門松や希望の旅の一里塚』と考えを新にしているのであります……」
倫平先生はにこにこ笑っておられた。
三月期は代議員会がすばらしかった。あれほどの代議員会は、もう絶対に出来まいと今もって信じている。
二年生は、生徒会の経験者と、その道の猛者ばかりであったし、一年生は経験者こそいなかったが、二年生に輪をかけたいくらい華々しかった。
今でこそ、入試対策で悟り切った面構をしているが、市村、浜本、松島、小谷四君をはじめ壮々たるもので、ずらっと各学年別にならんで(その頃は机をコの字型にならべて学年別にすわった。)二年三年とはげしい論戦がみられた。
僕等総務は、文化部の活動を活発化するため、いろいろと研究し文化活動を活発化三ケ年計画を上提し、クラブの削減を行い、総務の統括権を強化しようとした。
代議員会で、ものすごい論争となり、定例会の会期一週間はまたたく間に過ぎ、最後に修正可決されたが、総務は不満として、議場から退場し、別室で、総務委員総辞職か、代議員会解散かを協議した。総辞職に決定しその旨代議員会に通知した。六時近くだった。
代議員会は、時間延長を決議し、討論の結果、同議案を再討論する一方、総務の慰留に努めることを決議し、再び総務との質疑応答が行われ、双方妥協案を満場一致可決した。
予算編成が開始されると、書類提出に遅れたクラブは、設立を認めぬ旨を通知した。
美術部とサッカー部が部員不足で未提出であったので両部の存続を取りけすと、部員が泣き顔でやって来た。相手にしなかったら天満屋先生のところに泣きついたらしかった。
「今度だけは、ゆるしてやってくれ。充分しぼっておくから。」といわれたので、やむなく存続を認めた。
総額164万円の予算大綱の審議には、生徒会中心でのぞみ、学校に対するすべての補助を打切り、クラブ予算も出来るだけ重点的にした。生徒会顧問の先生方は困られたようだが、強引におしとうした。
クラブの反撃もすごかった。
柔道部の人が、予算審議の代議員会の途中、僕をよび出して真赤になってどなりつけた。
「あいだけで足ると思うとか。」
「仕方ありませんよ。」少しこわかったが、僕は図々しかった。
「わいは、おい達の練習ば知っとっとか。」
「でも、それは予算とは関係ありませんし、柔道部にだけやるわけにはいきません。」
「なんて」そう云って肩をどんとをついた。すごい力だった。
「わいは、あとで柔道場にこい。おいが立ちきらんごとしてやっとけん。」といってちょっとそりかえったので、僕は、又、例の如くにたりと笑って
「僕は弱虫で、泣き虫ですから、行ききらんです。」といった。すると妙な顔をしたので、又、にたりと笑うと、力みかえっていたのがあわてて
「あとでこいぞ、こんばぞ。」とわめきながらいってしまった。後で友人に、「ふくろだたきにするていいよっけん用心せろよ。」と注意された。僕はだまっていた。
予算は強引におしとうしてしまった。
総務の任期が切れる五月、遂に新聞部とけんかをした。新旧総務の座談会に新聞部を入れないといったのが原因だった。
今考えると他愛もないことだが、その頃は、
「今までこっちが何も云えないと思って、さんざん悪口を書きやがって今更おめおめということがきけるかい!」てな調子だった。
全総務委員に、新聞部に対しては黙秘権を使うように云った。新聞部は大あわてだった。三年生が出てきて、僕に文句を云った。僕はにたにた笑っているだけだった。
新総務十名が決定すると、僕等はさっさとひいて黙秘権の行使もやめてしまった。総務の座談会に新聞部は記事とりに出席した。あまりいい気はしなかった。
八月の休み、新聞部へ入った。徳富蘇峰を夢みてだった。もちろん父には内緒だった。
十月に発行した。二年生なので三年生の気も知らず書きたい放題書いた。今、それをひろげて読みかえすと、「毒舌甘味」にこんな文章を書いていた。
"野辺の虫の音に秋だなとしみじみ感じる。先月十九日は仲秋の名月、何はなくとも手近の秋草に心ばかりの月見団子の風情を味わいたいものであったが……月を鑑賞するのは各国人に共通した心理だが、月を見て「もののあはれ」を感じるのは、仏教が深く根をおろした日本での特色であるようだ。
大江千里の月みればちぢにものこそ悲しけれの歌に、日本人の月に対する情緒がよく
あらわされている。……
◆スポーツと共に秋は読書の季節、我々にはまだまだ読まねばならぬ本がどこにでも積んである。もちろん試験勉強も大切だが、それにおしこめてしまっては学生の悩みは深まるばかりである。
◆国破れて山河ありというが、河童が鳴く河、たぬきがおどる林、この国に継ぎ伝えられた幽玄の自然に心をはせることによって、あるいは文学の中に、思考の中に自己を見出すことによって、あるいは又、運動会、文化祭に若い情熱を燃やすことによって我々は心の憩を求め得ると同時に、失われようとする若い人間性が躍動するのではなかろうか"。
一年の後半以後僕の「美しい季節」だった。
本は、毎日1冊は必ず読んだ。めったに本を買ってもらえなかったので、昼食のパン代をためて買うことにしていたが、今頃だと、とても昼をぬくなんて出来ないのにその頃はさほど苦痛を感じなかったから不思議だった。
週末の夜のひとときを、本屋で過ごすのが楽しみだった。読んでしまったら、古本屋へ売った。だから、本棚には本が増えたことがなかった。それでも、いい本だけは残っていた。一年上級の伊藤さんもよく本を貸してくれた。
太宰治もその頃読み始めた。伊藤さんも人が悪いもので、まっ先に「人間失格」を貸して、読めといった。
気がすすまぬままに読んで、おどろいた。武者小路実篤や山本有三の崇拝者だったら読めるものではないような気がした。彼等のでは満足出来ないようになっていたけれどもやはり、再び太宰を読むには何か抵抗を感じた。
しかし、一度知ったリンゴの味は全く僕を魅了してしまい、僕の中に芽ばえかけていた、人間に対する疑惑と嫌悪と抵抗は一つのはっきりした性格となって現れ、目茶苦茶によみあさって、太宰の人間に対する、徹底した疑惑や嫌悪や抵抗の現れている演技の中に、人の子太宰のおさえてもあふれ出る、人に対する限りなき愛情のひそみを知った。
しかし、まだそれでも甘い考えのような気が僕を支配し、きびしきものをもとめてやまぬものとなし、カフカの「変身」は再び僕を混乱の世界へ導いた。
しかし、再びカフカを読む気はしなかった。その頃いくたびも、ハイネの詩集を手にし、啄木の詩集を手にしたけれども、その熱情中に全身を飛びこませるには、まだ数歩のへだたりを感じ、それは永久に縮まぬもののごとく感じられた。
抒情詩絶対の時期から、それに遂にあきたらず、叙事詩の偉大さを知ったのも、人間がいやになった僕の当然のことでもあった。
混乱した頭と、家にいるときの不快さは、ますます本を読ませ、人間をきらいにならせたし、一人ではいたたまれずに誰かにすがりつきたい衝動にかられた。
聖書も読んだ。思っていることをどんどん日記風に書きつけた。
二年になって、すぐの五月の初め、教会へ行った。しかし失望した。帰ってくると、父は、したたか酒を飲んでいて、僕をなぐりつけた。
教会に行けば必ず洗礼を受けて、クリスチャンになるものと決めているらしかった。だから、石橋家の墓はどうするんだといった。お前の母はどうするんだといった。仏間へつれていってすわらせ、燈明をともして線香をつけて説教をした。ずい分なぐられた。
それまでだまっていたが、母のことをいわれるのは、にが手だった。僕は母が欲しかった。僕の母が欲しかった。僕は仏壇の前で、「お母さん、何故僕等を残して死んじゃった。」といって泣いた。
太宰なんか読むから、こんなになるんだといった。「以後絶対読むなとはいわないが、読むな。」といった。いやないい方だった。太宰の自殺が気にくわないといった。
作家と作品とを完全に同一視していた。
父は全然本を読んだことがなかった。「お前がそんなに妙な本を読みたければ、菊池寛の『第二の接吻』でも読め。」などと云った。エロ本や姦通小説と間違えているようだっだ。本に関しては、全く無知だった。
「それは太宰治でも、みんながみんな悪いとはいわぬが……」というようないい方が僕はきらいだったし、今もなお嫌いである。理解のあるようないい方で、強引に自分の考えをおしつけるいい方だった。
数日後、「アイゼンハワーの兄弟」という本を買って来て、「読め」といった。僕は腹がたって、表紙のアイゼンハワーのにやけた顔までむかついた。読みもしないで、古本屋へたたき売った。
父には、若いもののの人生に対する悩みとか、苦しみとかは通じないようであった。そんな暇はぜいたくとでもいわれそうだった。
今までもっていた本が燃やされそうになったので、急いで友人の家へあずけた。家には参考書だけしか残らなかった。そうすることに何か前時代的ないやな気持ちと、自由の保護者とでもいいそうなヒロイズムを感じた。それでも、穴うめにされることはなかろうと思った。
ますます本を読んだ。
十二月に文芸雑誌「ざ・ふいのみなん」の第二号を発行した。りっぱなものだと思った。一号は四月に発行していた。費用はすべて友人達の寄付であった。西高の友人と二人で徹夜に近いことを数日つづけて原紙を切って作った。
「若さ」に対する無限の喜びを感じた。
三年になって家庭教師がつけられた。僕は、もっと本を読みたかった、もっといろいろなことを、社会を知りたかった。
ある本には、「試験勉強なんていやだ。本当の勉強がしたい。」と書いてあったが、僕には本当の勉強が何なのか解らなかった。しかし、それには、本当の勉強をするためには、試験勉強も、浪人生活も必要に違いないのだ。
英語が、二年生まで駄目だったので、英語ばかりした。
英語の先生は一週に二回こられたが、その進み方はものすごかった。だから、予習するのにどんどん追われた。しかし、その中に、楽しさがあった。通常試験では、二年の時とは比較にならぬほどの点をとったが、実力考査や模擬試験ではまだまだだった。
三年の一学期まで代議員をつとめた。一度総務を経験したものはまともに代議員はやれないと友人がいったが、その通りだった。
総務の中をよく知っているので、議案にしても徹底的につっこむと、下級生や女生徒は必ずこういって反対した。
「石橋さんのはひどすぎる。総務が可愛相だ。」
総務からはものすごく敬遠された。代議員は出て来たらめいわくというような顔をした。でも、僕は出てゆかないではおれなった。「それではいけない。」といわないではおれなかった。
二学期にも再び代議員に選ばれた。しかし、僕はその時強くことわったが、皆は全然うけつけてくれなかった。とうとう僕は机にうつぶして泣きだしてしまった。生徒会はもう自分とは何の関係もないように感じた。くやしかった。そして、皆がうけつけてくれないのが悲しかった。生徒会ではもはや過去の人になってしまったのが悲しかった。
友人が代わってくれた。
それで全く生徒会とは無関係になったようであった。しかし、やはり不安だった。次期の顔ぶれを予想すると暗然とした。そして、再び、選挙の時友の応援の為に講堂の壇上に立った自分を見出したのであった。
どんな可能性があったか解らなかったが、確かに僕の性格が変わったのは事実だった。だが心の中、少しは幼い頃のおとなしかった自分がなつかしい気がして、すべてから逃げそうだとするところにはやはり、いつも変わらぬ僕の性格があった。
自分の存在というものが、今は単に死にたくないから生きているとか、生きたくないからそのつらあてに生きているとか云えなくなってしまったし、又、社会の為、人類の為などとはとうてい云いきれそうにもない。
しかしこの三年の間、僕は「平凡」という言表現や読書には何よりも厳しさを追求したはずなのだ。
その追求に破れると、空の彼方や山の奥深くの何かすばらしいものにあこがれ、その衝動をおさえきれないで詩を読み、野山を逍遥したはずなのだ。
しかし、それでも何かものたらなかった。身を焼きこがすほどの炎。
酒ならば、焼酎やウイスキーをさらにコンデンスして、どろっとした、舌にあてると舌が燃えるような酒。
恋ならば、椿姫や八百お七のような身をとろかし、すべてを忘れさるようなもの、とにかく、このなまぬるい世の中がいやだった。ぬるま湯につかっているような気持、社会がかもし出す焦燥、喧騒、――。
人間に対する憎悪と、人の子たる僕の人に対する限りなき愛着。
僕には解らなかった。
何がこの世で一番大切なのかが解らなかった。けれども、僕が欲しがっているものはただ一つしかなかった。優秀な通知表でも、大きな家でも、金でも、名誉でもなかった。
僕の愛、表現出来ないままの野育ちの僕の愛を、両腕をひろげ、微笑んでうけとめてくれる母が欲しかった。高校になって今更なにを女々しい、ではなかった。僕は、それを求めて、つきあたり、転び、さまよってきたのだ。
僕は今、この三年の間僕を導いて下さったあらゆる先生方に、心からのお礼を云いたいし、世のお母様方や、将来そうなるであろう人々に、子を残しては絶対に死んではならぬと訴えたいのだ。
それが、これまできびしい父の手一つで育ってきた僕の、父に対する感謝と、それ一つでは解決出来なかった僕の心の飾りない姿なのだ。